第一章 静かな部屋の住人

八月の日差しは容赦がなかった。
蝉の声がアパートの壁に反響している。けれど、その狭いワンルームに籠もるタケトには、時間の経過を示す唯一の音にしか聞こえなかった。
時計の針はいつの間にか午後二時を回っている。カーテンを閉め切った室内には、わずかな光しか差し込まない。部屋の片隅で、タケトは小柄な体を浅くソファに埋め、冷めきったインスタントコーヒーを手に、虚ろな目で天井を眺めていた。
身長一五八センチ。大学に進学したものの、二年で退学し、今は無職。二十三歳という年齢は、世間から見ればようやく社会に踏み出しているはずの若さだ。しかし、彼の時間は、退学を決意したその日から、ほとんど動きを止めていた。
朝に起きる理由が見つからない。昼夜逆転も、もはや修正する気力がない。コンビニに出向くのもひと苦労で、弁当の残り香と、散らかった書類だけが生活の名残を主張している。時おり母から届く連絡も、未読のまま積み重なっていく。
――「お前は、どうするつもりなんだ」
画面に表示される短い問いかけ。その一文を見るたびに胸が重くなり、結局通知を消してしまう。罪悪感はある。けれど、返す言葉を持たない。
タケトの耳は敏感に、外の世界に反応していた。アパートの外廊下を行き来する学生たちの笑い声。どこかで響く子どもの泣き声。自転車のベル。――それらすべてが、彼には「自分には関われない生活」の音として届く。
扉の外では確かに何かが進行しているのに、自分の部屋だけは凍結された時間の中に閉じ込められている。
けれど、彼がそう思い込んでいられるのもあとわずかだった。
その日、インターホンが鳴った。
珍しいことではない――宅配便だった。ネットで頼んだ日用品が届いたのだろう、と彼は反射的にカーテンの隙間を確認する。
けれど、画面に映ったのは、想定していた作業服姿の配達員ではなかった。
そこに立っていたのは、一人の女性だった。
白いブラウスに柔らかなベージュのスカート。ポニーテールの黒髪が揺れている。直射日光を受けても涼しげな表情を崩さないその姿は、大学時代に廊下ですれ違った才媛を、ふと連想させた。
数秒の静寂ののち、もう一度インターホンが鳴った。
タケトは慌ててスピーカーをオンにした。
「……はい」
自分でも驚くほど乾いた声が出る。
『こんにちは。お隣に越してきた香奈美といいます。ご挨拶に伺いました』
言葉は明るく、それでいて気品のある柔らかさを纏っていた。
彼女は軽く会釈し、インターホンのカメラ越しにも礼儀正しさが伝わってくる。
タケトの胸に緊張が走る。彼はしばらく返事に詰まり、無言の数秒が過ぎた。
『あの……ご在宅でなければ、また改めます』
そう言われ、タケトは反射的に「います」と答えてしまった。
玄関に向かう足取りはぎこちない。それでも、扉を開けた。久しぶりに外気が部屋に流れ込み、熱気と同時に、心に固まった澱のようなものをかき回していく。
そこに立つ彼女――香奈美は、タケトの想像以上に、外の世界そのものをまとっていた。
「はじめまして。隣に越してきました、香奈美と申します。よろしくお願いします」
白い紙袋に入った菓子折りを差し出しながら、小さく微笑む。態度に隙がないのではなく、自然体の余裕のように見える笑顔だった。
タケトは受け取る手が震えるのを止められない。
「……あ、ありがとうございます」
実に半年ぶりの、正しい「挨拶」だった。
香奈美が去ったあと、タケトはしばらく玄関に立ち尽くしていた。
生活の淀みを破るように差し込んできた光。扉一枚の向こうに、当たり前の人間関係が存在しているという現実。
自分には遠いものと決めつけていたはずの世界が、ふとした拍子に、すぐ隣に現れてしまった。
紙袋の中には丁寧に包装された焼き菓子。リボンの色さえも、彼の部屋の陰鬱を揺さぶる。
――どうすればいいのか。
タケトの心は戸惑いとともに、どこかで微かに「期待」の響きを伴っていた。
彼は知らぬ間に、自分の閉ざした扉の向こうに、小さな裂け目が生まれてしまったことを、理解したのだった。

第二章 陽だまりの訪問者

翌朝、タケトは妙に眠りが浅かった。
夜更かしすることが習慣になり、いつもなら昼過ぎまで起き上がらないのに、今日は八時前にまぶたが開いた。理由は分かっている。昨日の出来事が、彼の心に小さなさざ波を立てたのだ。
隣に引っ越してきた女性――香奈美。
わずか数分の会話、わずかな笑顔。それだけで、タケトの中に忘れていた感覚が蘇る。かつて大学に通っていた頃、講義室で感じたあの人のざわめきや視線、ほんの些細な交流が心を温めるという感覚。
「ただの挨拶だ」
そう自分に言い聞かせる。けれど、胸の奥に残った感触は、明らかにそれ以上の意味を持っていた。
午前十時を回った頃、タケトは珍しく散らかった部屋の机を片づけ始めた。理由は自分でも曖昧だ。ただ、昨日のままの無秩序と、渡された焼き菓子の包装が同居していることに、耐えられなかった。
そのときだった。ドアの向こうから軽やかなノックの音が響いた。
「……?」
凍りついた。インターホンは鳴らず、直接ノック。ということは、また香奈美だろうか。
心臓が不安定に跳ねる。出るべきか、無視すべきか。逡巡ののち、彼はおそるおそる扉を開いた。
やはりそこに立っていたのは香奈美だった。昨日と同じ白ブラウスにカーディガンを羽織り、手にはスーパーのレジ袋を提げている。
「おはようございます。突然すみません」
彼女は少しだけ困ったように笑った。
「実は、荷物の整理をする時に、段ボールを重ねすぎちゃって……良かったら、ちょっと手伝っていただけませんか?」
その言葉に、タケトは息を飲んだ。
「お願いされる」という行為が、彼の日常には久しく訪れていなかった。
誰かに求められること。それ自体が、ひどく古びた感触だった。
「……あ、えっと……」
「もちろん無理なら大丈夫です。でも、もしお時間あれば……」
香奈美の声音には、自然な礼儀と同時に「相手を信じている」という温度があった。
断ろうとする気持ちと、逃げ場を失う不安が入り混じる。結局、タケトは小さくうなずいていた。
「……はい」
隣の部屋は、引っ越し直後らしく段ボール箱が積み重なっていた。
けれど不思議と雑然とは感じなかった。ラベルが整然と貼られ、必要なものと不要なものが規則的に仕分けされている。香奈美という人間の几帳面さが、そのまま映し出されているようだった。
「ここを持ってもらえますか?」
タケトが片方を持ち上げる。段ボールは軽い。けれど、その動作のぎこちなさは自分でも分かるほどだった。
香奈美はそんな彼の様子に気づいてか、口元を和らげた。
「ありがとうございます。助かります」
その一言が、胸をじんわりと満たしていく。
実際には、大した作業ではない。ただ数分間、二人で段ボールを移動させただけだ。しかしタケトにとっては――半年ぶりに「誰かと一緒にことを成し遂げた時間」だった。
「お疲れさまでした。……お礼といってはなんですが」
香奈美は冷蔵庫から麦茶を取り出し、コップに注いで差し出した。その仕草は自然で、家庭的な温かささえ漂わせていた。
タケトは無言で受け取り、唇を濡らした。冷えた麦茶が喉を通るたび、乾いた心に沁みる。
「お隣にどんな方が住んでいるか不安だったんです。でも、お優しい方で良かった」
香奈美はそんなふうに語る。タケトは思わず視線を落とした。
「優しい」とは、自分に最も似合わない言葉だと思っていた。何ひとつ社会に適応できず、家族を心配させ、逃げ続けてきた自分が、優しいはずがない。
「……あの、僕は……」
言いかけて、言葉が喉に詰まる。自分の素性――無職で、夜に活動し、誰とも関わらない日々――をどう説明すればいいのか。
だが香奈美は、その続きを尋ねてはこなかった。ただ、淡い笑顔のままコップを小さく掲げて言う。
「これから、お互いよろしくお願いしますね」
タケトは頷くしかなかった。その瞬間、自分の心に降り注いだのは、陽だまりに似た安堵感だった。
部屋に戻ったタケトは、深いため息をついた。
香奈美に頼まれ、ほんの数分過ごしただけなのに、全身が妙に疲れている。
だが同時に、その疲労は奇妙に心地よかった。筋肉を使った倦怠感ではなく、長く麻痺していた心が少しだけ動いた証のように思えた。
机の上には香奈美からもらったコップが残っていた。うっすらと水滴がついたその硝子の輝きが、彼の孤独な部屋にひどく場違いで、それゆえに眩しかった。
――自分の生活は、このままでいいのか。
そんな問いが胸の底に生まれ、タケトはそっと目を閉じた。
隣人の存在は、彼の閉ざされた世界に確かに揺らぎをもたらしつつあった。
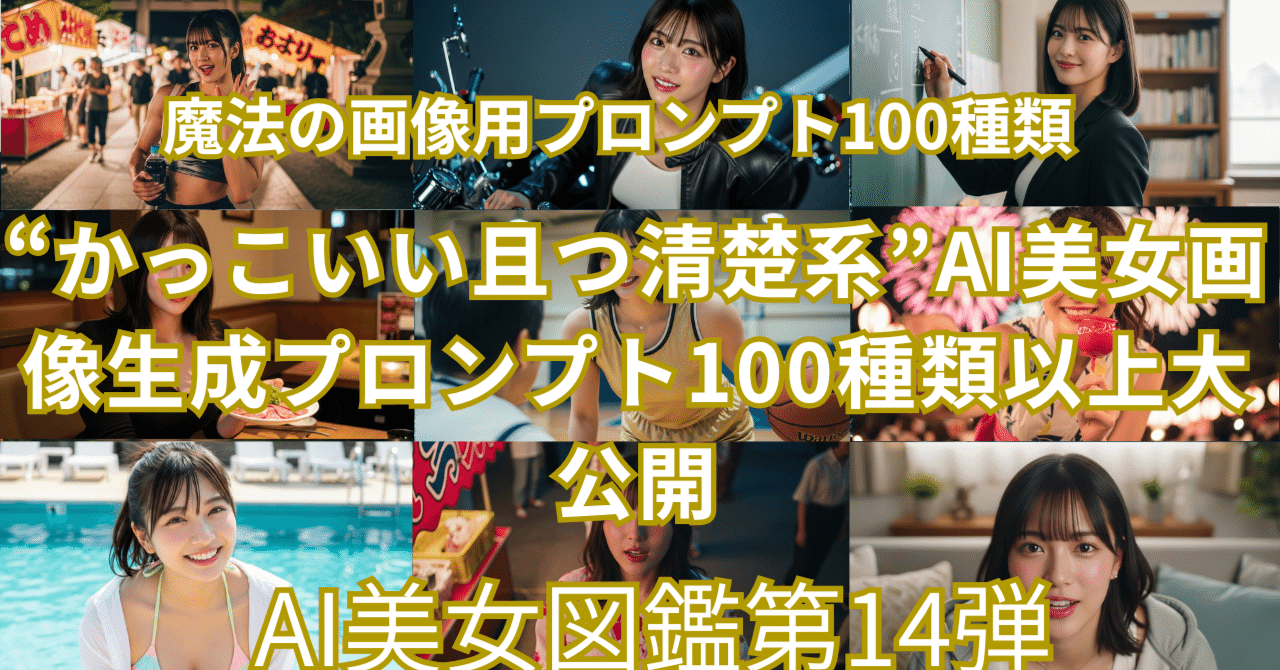
第三章 小さな光、小さな一歩

いつものようにカーテンを閉めきった部屋の中で、タケトは机の上のコップをぼんやりと見つめていた。昨日、香奈美に出された麦茶の余韻。それはただの水滴の跡にすぎないのに、どこかまだ「温度」を残している気がしてならない。
ここ半年あまり、自分の部屋は密閉された水槽のようだった。誰とも交わらず、外界の音はただ遠くに響くエコーでしかなかった。だが最近、その水槽に亀裂が入った――隣から訪ねてきた女性の声と笑顔によって。
気づけば、タケトはスマートフォンを手に取っていた。時間は午後四時。
ちょうど外が夕暮れに染まる頃合いだ。
コンビニに行けば、アイスコーヒーでも買える。行くだけなら五分もかからない。
それだけのことが、とてつもない試練に感じられる。
けれど扉の前に立ったとき、不意に脳裏に浮かんだのは香奈美の声だった。
――「よろしくお願いしますね」
柔らかな笑顔と共に差し出されたその言葉。
深呼吸をひとつ。タケトは意を決して、久しぶりにドアノブを回した。
午後の大気はむっとするようにまとわりつく。
だがタケトの頬を撫でた風は、久しく感じていなかった“生きた”感触だった。
ほんの数歩、外廊下を歩いただけで膝が震える。視線は下に落ち、肩が強張る。誰かに見られているのではないか、笑われるのではないか、そんな不安が渦巻いた。
石のように固まった身体を励ますために、彼は心の中で言い聞かせる。
――アイスコーヒーを買って帰るだけ。それならできる。
そうやって一歩を踏み出そうとした、その時だった。
「タケトさん?」
背後から自分の名を呼ばれる。息が止まる。
振り向けば、やはり香奈美がいた。スポーツバッグを肩から下げ、汗が光る額をタオルで拭いている。運動帰りなのだろう。
「あ……」
喉が乾いた音しか出てこない。
香奈美は意外そうに目を丸くしたあと、優しく微笑んだ。
「お出かけですか?」
「……コンビニに」
自分から口に出したことにタケト自身が驚いた。外に出る理由をわざわざ説明したのは、いつぶりだろう。
「いいですね。私もちょうど寄ろうと思っていたんです。一緒に行ってもいいですか?」
唐突な提案に、タケトは答えを失った。
しかし、断る勇気も持ち合わせていない。数秒の沈黙ののち、彼は小さくうなずいた。
二人で並んで歩く道すがら、香奈美は自然に言葉を紡いでいった。
大学では運動部に所属していること。来月には大会があること。サークル仲間と研究室の忙しさを両立するのに苦労していること。
タケトは相槌を打つだけで精一杯だった。だが不思議と、彼女の話は耳に心地よい。自分の世界には存在しなかった「前に進もうとする力」が彼女の言葉には宿っていた。
「……タケトさんは、普段はどうされてるんですか?」
不意に向けられた問いに、足が止まりそうになる。
隠すことはできない。けれど、正面から答える勇気もない。
「……ほとんど、家にいます」
声はかろうじて届く程度にしか出なかった。
だが香奈美は否定も詮索もせず、ただ穏やかに頷いた。
「そうなんですね。では今日は、ちょっとした冒険ですね」
その言葉に、タケトの胸に微かな熱が灯った。
「冒険」という響きは、自分の弱さを責めるのではなく、小さな一歩を肯定してくれている。
コンビニに着いたとき、タケトはようやく自然に息をついた。
冷気が出迎える店内。アイスコーヒーを手に取り、レジへと向かう。ただそれだけの行為が、信じられないほど大きな達成感となって彼を満たしていた。
「お疲れさまです」
会計を終えると、香奈美が小さく笑った。
「無事にミッション完了、ですね」
タケトは言葉を返せず、ただ頷くだけだったが、胸の奥にほんの小さな自信が芽生えているのを確かに感じていた。
帰り道、夕焼けに染まる街を二人で歩く。
香奈美の横顔を盗み見たタケトは、一瞬だけ思った。
――この人は、太陽みたいだ。
まぶしくて、近づきすぎれば焼かれてしまいそうで。
けれどいまはただ、その光の欠片を浴びるだけで、自分の中の氷が少しずつ溶けていくのを感じていた。
その夜。
タケトは自室に戻り、ベッドに腰を下ろすと、思わず小さく笑った。
理由はうまく説明できない。ただ、今日という日は「ただ消費した一日」ではなかった。
――自分は確かに外に出た。
麦茶のコップと並んで机に置かれたアイスコーヒーの空きカップが、それを証明していた。
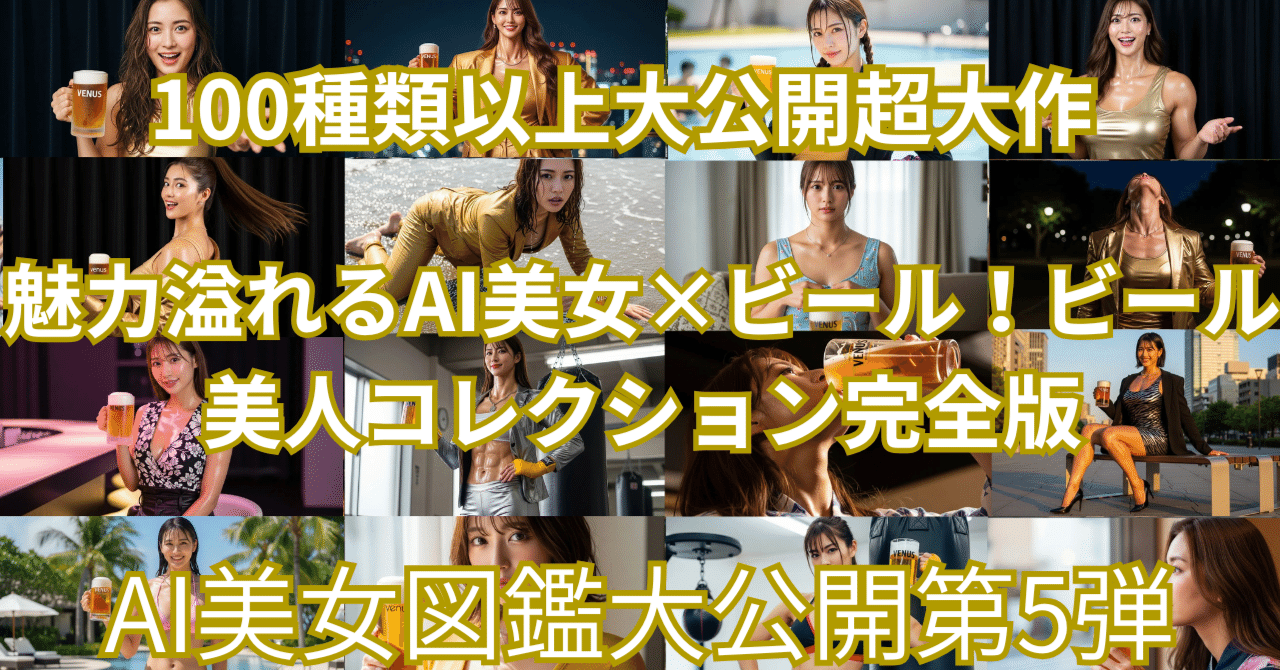
第四章 揺れる心、遠い過去

その数日後。
タケトは机に向かっていた。と言ってもノートや本を開いているわけではない。薄い埃の積もった古いUSBメモリを手に取り、ただ見つめていただけだ。
それは大学時代に使っていたものだった。レポートや過去の資料が保存されている。電源を入れて確認する勇気はない。けれど捨てることもできず、気づけば何度目かの「見つめて終わる」だけの時間をまた繰り返していた。
外に出た。香奈美と話した。小さな一歩を踏み出した。
だが、歩みかけた先で、どうしても突き当たる過去がある。
――大学を辞めた理由。
成績不振というわけではなかった。
だが、講義も研究室も、居場所と呼べるものはなかった。周囲が仲間と笑い合う姿を見るだけで心が縮こまり、誰かに話しかけられると舌がもつれる。実力不足を痛感する場面が続くと、やがて足も教室から遠のいた。
最後に研究室の教授に呼び出された日のことを、タケトはありありと覚えている。
「進路を真剣に考えるべきだよ」
その言葉のあとに浮かぶ沈黙こそが、自分が見放された瞬間だったと、いまだに心を締めつける。
夕暮れ。外廊下に差し込む橙色の光が、カーテンの隙間から伸びてきた。
その時、またあの声がした。
「タケトさん、います?」
香奈美の声だった。
慌てて立ち上がり、扉を開けると、彼女はジャージ姿で立っていた。練習帰りらしく、まだ頬が赤い。
「こんばんは。帰りにお惣菜を買いすぎちゃって……もし良かったら、一緒にどうですか?」
香奈美はスーパーの袋を掲げる。中からは焼き魚や煮物の香りが漂ってきた。
タケトは戸惑いながらも、応じるしかなかった。気づけば二人は狭いテーブルを挟み、簡素な夕食を並べて座っていた。
「タケトさんは、ご家族とは?」
香奈美が、何気ない調子で尋ねてくる。
箸を止め、タケトは答えを探した。
「……実家には、たまに連絡が来ます。母が……心配してるんだと思います」
「会いには?」
「……行けていません」
重苦しい沈黙が落ちるかと思ったが、香奈美はただ頷いて煮物を口に運んだ。
追及しない。その自然体が、かえって胸に突き刺さる。
数口の食事ののち、タケトはふと口を開いた。
言葉が漏れ出てしまったのだ。
「……僕、大学を辞めました」
香奈美の手が止まる。だが顔色を変えることはなかった。
タケトは続けた。
「中途半端で、周りについていけなくて……。友達も作れなくて……結局、逃げてしまったんです。あの日から、僕は止まったままです」
声に震えが混じった。自分がどれほど惨めな人間なのか、さらけ出すようで耐え難かった。しかし、もう隠すことはできなかった。
香奈美はしばらく黙って聞いたのち、静かに言葉を置いた。
「……私も、逃げたことありますよ」
タケトは驚いて顔を上げた。香奈美のような眩しい存在が、逃げた?
「高校の時、ずっとバスケを続けてきて、推薦で大学にも入れました。でも……膝を痛めて、大事な大会で出られなかったんです。そのとき、全部終わった気がした。練習にも顔を出せず、ベッドから起き上がれない日が続きました」
その声には、苦い記憶を噛みしめるような重みがあった。
「でも……支えてくれる人がいて、もう一度立ち上がろうと思えたんです。私がすごいんじゃなくて、誰かが差し伸べてくれた手をつかんだだけ」
タケトは何も言えなかった。ただ彼女の言葉が、自分の奥深くにじわりと染み込んでいく。
気づけば食卓は空になり、窓の外は群青色へと変わっていた。
香奈美は食器を軽くまとめながら、ふと笑った。
「タケトさんも、いつかそうなるんじゃないでしょうか。まだ止まってる時間を、少しずつでも進めていける。私は……そう思います」
そのとき、胸がざわめいた。
過去の重さは消えはしない。だが、香奈美のように「共有してもいいのだ」と思えたこと自体が、初めての感覚だった。
夜、自室に戻っても、タケトの耳には香奈美の声が残っていた。
――「逃げたことありますよ」
自分だけが劣っているわけじゃない。
挫折や後悔は、誰にでもある。
そう思えた瞬間、胸の奥に長く居座っていた暗闇が、ほんの少しだけ退いていくのを感じていた。

第五章 夜の対話、見えざる未来

その夜は、ひどく蒸し暑かった。窓を少し開けても、外から流れ込んでくるのは湿った風ばかり。ベッドに横たわりながら、タケトは胸の奥がざわついて眠れずにいた。
――「私も逃げたことありますよ」
――「誰かが差し伸べてくれた手をつかんだだけ」
香奈美の言葉が、何度も反芻される。
彼女もまた過去に立ち止まった時期があったこと。けれど、そこから進むことを選んだこと。
タケトは、枕元で点滅するスマートフォンの光に目をやった。未読のままのメッセージがある。
――母からの「元気にしてる?」という短い問いかけ。
小さな文言が、不思議なほど重かった。
時計の針が十一時を回ったころ、廊下の方から足音がした。
思わず耳をそばだてると、軽やかなノック音が響く。
「夜分にすみません、タケトさん。まだ起きてますか?」
香奈美の声だった。
慌てて部屋着を直し、扉を開けると、彼女は部屋着姿のまま立っていた。手には温かそうなカモミールティーのカップが二つ。
「眠れなくって……。よければ一緒にどうですか?」
思わず頷いてしまい、タケトはリビングへ彼女を招いた。
二人、床に座り込んでカップを手にする。ハーブの香りが狭い部屋に広がり、昼間の蒸し暑さを忘れさせてくれる。
「タケトさん、この部屋……落ち着きますね」
「……そうですか?」
「はい。すごく静か。でも、それが悪い意味じゃなくて。……私が一人で考え込みたい時、こんな部屋があったらいいなって思うかも」
香奈美はカップを口に運びながら、そう言った。
タケトは少し戸惑った。自分にとって、この部屋は“逃げ場”であり“鎖”でもあった。けれど、香奈美には“静けさ”と映る。
同じ場所でも、人によって意味が変わる。その事実が、奇妙に心を軽くした。
「ねえ、タケトさん」
香奈美が、少し表情を改める。
「生きていると、どうしても『自分なんか』って思う瞬間、ありますよね」
タケトは視線を落とし、呼吸が詰まる。彼女にとっては「ある瞬間」なのだろう。自分にとっては「ずっと」だった。
香奈美は続ける。
「でも、私は思うんです。“弱さ”と“無価値”は違うって。逃げてしまうことはあっても、その人に大事なものがないわけじゃない」
その言葉は、タケトの心にゆっくりと沈んでいった。
「……僕、自分には何もないと思ってました。逃げてばかりで……。価値なんてあるはずがないって」
絞り出すように口にすると、香奈美は小さく首を振った。
「そんなこと、私が今日受けた手助けだけでも否定できます。あの段ボールを運んでくれたことも、一緒にコンビニに行ってくれたことも。私にとっては十分、大きなことでした」
タケトの胸の奥が熱くなった。自分の些細な行動が、誰かにとって「意味」のあるものになっていたとは。
「……僕にも、何かできるんでしょうか」
呟いた問いは、半ば無意識だった。
しかし香奈美は迷わず答えた。
「できますよ。私が保証します」
強く、でも優しい声だった。
タケトは飲みかけのカップを両手で包みこみながら、視界がぼんやりとにじみそうになるのを堪えた。
その後、二人はたわいのない話をした。大学の話、スポーツの話、好きな映画、苦手な食べ物。
気づけば午前零時を過ぎていた。香奈美が立ち上がり、カップを流しに置いて帰り支度をすると、タケトの心には奇妙な満足感が残っていた。
「じゃあ……おやすみなさい、タケトさん」
「……おやすみなさい」
別れ際、言葉を交わすその一瞬で、確かに自分は“世界の外側”から少し戻ってきているのだと感じた。
部屋に一人残りながら、タケトは窓の外を眺めた。夜空には星がわずかに瞬いている。
――まだ遠い。手を伸ばしても届かない。
けれど、それが「見える」という事実だけで十分だった。以前は闇しか見えなかったのだから。
「……僕も、誰かの役に立てるのかな」
未来はまだ霞んでいる。
しかし、心の底に微かな願いが芽生えた。
自分もまた、いつか“誰かを支える”ことができるのではないかと。
第六章 扉を開ける朝
秋の気配が忍び寄っていた。
窓を開けると、夏の蒸し暑さは和らぎ、ひんやりとした空気が頬を撫でる。久しぶりに、タケトは朝の光を自分の部屋で感じていた。
机の引き出しには、一枚の履歴書。震える手で何度も書き直し、ようやく完成させたものだ。小さなアルバイトの求人票を見つけて、応募の電話をかけた。声が震え、途中で切られてしまうのではと怯えながら。それでも最後まで話し終え、「面接に来てください」と返事を得られた。
予約されたその日は、今日。午前十時。
玄関鏡に映る自分を見下ろす。シャツに袖を通し、髪を整え、靴を磨いた。
――ありふれた格好。でも半年以上も、外に本気で出たことがない自分にとっては、戦闘服に近い。
「本当に大丈夫だろうか」
胸の奥で恐怖がうねる。扉の向こうにあるのは、拒絶かもしれない。冷笑かもしれない。
だが、そのとき聞こえてきたのは隣の部屋の声だった。
「タケトさん、いってらっしゃい」
振り向けば、廊下に香奈美が立っていた。
スポーツウェア姿で、朝練に向かう途中だったのだろう。彼の手に握られた履歴書の封筒に気づいたのかもしれない。
「……知ってたんですか?」
驚くタケトに、香奈美は穏やかにうなずいた。
「ええ、昨日すれ違ったとき、顔を見れば分かりました。……覚悟を決めた人の表情だったので」
言葉を返せなかった。視界がにじみそうになるのを、必死で堪える。
香奈美は微笑み、短く言った。
「大丈夫です。扉を開けるのは、もうタケトさん自身なんですから」
扉のノブに手をかける。
汗ばむ掌。これまで何度も触れたその金属の冷たさが、今日は違って感じられる。扉の向こうが「檻」ではなく、「入口」に見えた。
深呼吸をひとつ。胸を張る。
ギギ、と音を立てて扉が開く。
差し込んでくる光は、夏の日差しとは違う、やわらかで澄んだ秋の陽射しだった。
駅へ向かう道を歩き出す。足取りは不安定だが、確かに前に進んでいた。
道端の草の緑も、街を行き交う人々の声も、以前とは違って聞こえる。――自分がその一部に戻ろうとしているのだと思うと、胸がざわついた。
面接に通るかどうかなんて分からない。失敗するかもしれない。
けれど、それでいい。倒れても、また起きればいい。香奈美だって、膝を痛めて立ち止まったあと、また自分で立ち上がったのだから。
ふと、スマートフォンを取り出した。
母からの未読通知はまだ残っている。
勇気を振り絞り、短く返信を打った。
――「少しずつ動き始めています」
送信ボタンを押した瞬間、胸の奥が軽くなる。
小さな一歩。でも、自分にとっては大きすぎる一歩だった。
駅前の建物に近づくと、反射ガラスに自分の姿が映る。
小柄で目立たない青年。だが、その表情にはほんのかすかな――けれど確かな意思が宿っていた。
タケトは深呼吸をひとつし、面接会場の扉を開けた。
アパートの窓辺に立つ香奈美は、その小さな背中を見送っていた。
秋の光に包まれたその姿は、たしかに「歩き始めた人」に見えた。
彼女は小さくつぶやいた。
「……いってらっしゃい、タケトさん」
そして、そっと笑みを浮かべながら自分の練習バッグを肩にかけ、朝の道へと歩き出していった。

第六章 扉を開ける朝

秋の気配が忍び寄っていた。
窓を開けると、夏の蒸し暑さは和らぎ、ひんやりとした空気が頬を撫でる。久しぶりに、タケトは朝の光を自分の部屋で感じていた。
机の引き出しには、一枚の履歴書。震える手で何度も書き直し、ようやく完成させたものだ。小さなアルバイトの求人票を見つけて、応募の電話をかけた。声が震え、途中で切られてしまうのではと怯えながら。それでも最後まで話し終え、「面接に来てください」と返事を得られた。
予約されたその日は、今日。午前十時。
玄関鏡に映る自分を見下ろす。シャツに袖を通し、髪を整え、靴を磨いた。
――ありふれた格好。でも半年以上も、外に本気で出たことがない自分にとっては、戦闘服に近い。
「本当に大丈夫だろうか」
胸の奥で恐怖がうねる。扉の向こうにあるのは、拒絶かもしれない。冷笑かもしれない。
だが、そのとき聞こえてきたのは隣の部屋の声だった。
「タケトさん、いってらっしゃい」
振り向けば、廊下に香奈美が立っていた。
スポーツウェア姿で、朝練に向かう途中だったのだろう。彼の手に握られた履歴書の封筒に気づいたのかもしれない。
「……知ってたんですか?」
驚くタケトに、香奈美は穏やかにうなずいた。
「ええ、昨日すれ違ったとき、顔を見れば分かりました。……覚悟を決めた人の表情だったので」
言葉を返せなかった。視界がにじみそうになるのを、必死で堪える。
香奈美は微笑み、短く言った。
「大丈夫です。扉を開けるのは、もうタケトさん自身なんですから」
扉のノブに手をかける。
汗ばむ掌。これまで何度も触れたその金属の冷たさが、今日は違って感じられる。扉の向こうが「檻」ではなく、「入口」に見えた。
深呼吸をひとつ。胸を張る。
ギギ、と音を立てて扉が開く。
差し込んでくる光は、夏の日差しとは違う、やわらかで澄んだ秋の陽射しだった。
駅へ向かう道を歩き出す。足取りは不安定だが、確かに前に進んでいた。
道端の草の緑も、街を行き交う人々の声も、以前とは違って聞こえる。――自分がその一部に戻ろうとしているのだと思うと、胸がざわついた。
面接に通るかどうかなんて分からない。失敗するかもしれない。
けれど、それでいい。倒れても、また起きればいい。香奈美だって、膝を痛めて立ち止まったあと、また自分で立ち上がったのだから。
ふと、スマートフォンを取り出した。
母からの未読通知はまだ残っている。
勇気を振り絞り、短く返信を打った。
――「少しずつ動き始めています」
送信ボタンを押した瞬間、胸の奥が軽くなる。
小さな一歩。でも、自分にとっては大きすぎる一歩だった。
駅前の建物に近づくと、反射ガラスに自分の姿が映る。
小柄で目立たない青年。だが、その表情にはほんのかすかな――けれど確かな意思が宿っていた。
タケトは深呼吸をひとつし、面接会場の扉を開けた。
アパートの窓辺に立つ香奈美は、その小さな背中を見送っていた。
秋の光に包まれたその姿は、たしかに「歩き始めた人」に見えた。
彼女は小さくつぶやいた。
「……いってらっしゃい、タケトさん」
そして、そっと笑みを浮かべながら自分の練習バッグを肩にかけ、朝の道へと歩き出していった。



コメント